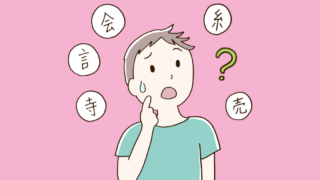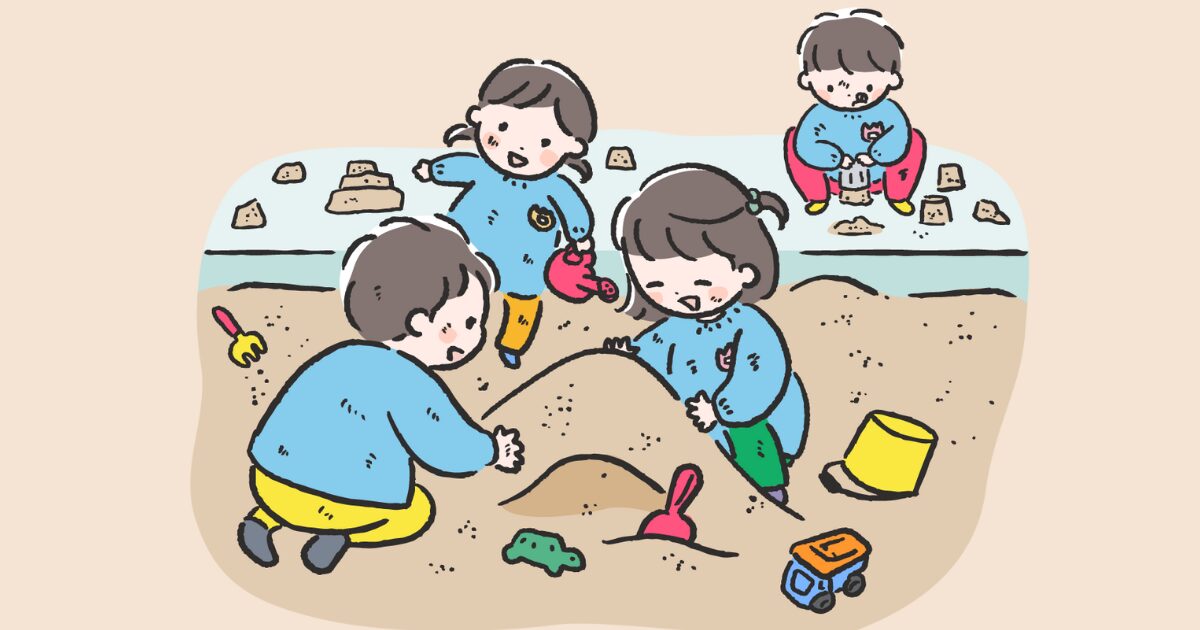このブログでも何度も出てきている「非認知能力」というキーワード。この能力を身につけたことの成果は、少しあとになって見えてくるので、「あと伸びする力」とも呼ばれています。
その鍵となるのが、子どもの主体性とあそび。特に、五感を通して遊び込むことが重要で、「あそび」を通じて非認知能力が育つと言われています。
しかし、現代では朝から晩まで、外で近所の異年齢の友達と思い切り遊ぶ機会が少なくなっています。では、どうすれば子どもにとって良い「あそび」ができるのでしょうか?
この記事では、「非認知能力を育てるあそびのレシピ」から、現代の生活に合った遊びのヒントを紹介していきます。
非認知能力とは?
非認知能力とは、数値では測れない、知識や学力とは異なり、意欲や忍耐力、共感力、自己コントロール力など、社会で生きていくために必要な力のことを指します。
50年以上前から続く「ペリー就学前プロジェクト」
アメリカで50年以上続くヘックマンらによる研究「ペリー就学前プロジェクト」によると、就学前に大人から優しく対応された経験を持つ子どもたちは、以下のような成果を得ていることがわかりました。
- 学力や収入が高い
- 自己コントロールができ、意欲的に取り組める
- 他者と上手にコミュニケーションが取れる
また、就学前に教科学習の先取りをしても、その効果は短期的であり、数年後には早期教育を受けなかった子に追いつかれることも判明しました。
つまり、将来的に長く持続する力は「非認知能力」であり、これこそが子どもの成功につながる大切な力なのです。
もっと詳しい非認知能力については▶️「非認知能力とは?教育の新常識を知る1冊『子どもの才能を伸ばす 最高の子育て』」
非認知能力を育むためのポイント
アタッチメント(愛着形成)
第一に、アタッチメントと呼ばれる、基本的な信頼感を持つことが何よりも大事です。
ありのままの自分を暖かく受け止めてくれる大人がいることを認識することで、自分の気持ちをコントロールして、自発的に物事に取り組むようになります。
アクティブラーニング
子どもが自分で選んだことに、夢中であそぶことで「問い」や「探求心」が生まれ、主体的に学ぶ力が育ちます。
子どもが自分で選び、考え、試行錯誤しながら遊ぶことが「アクティブラーニング」につながります。夢中になって遊ぶことで、以下のような能力が身につきます。
- 課題を解決する力
- 創造力や発想力
- 集中力
つまり、乳幼児期には、親が選んだ習い事をたくさんするより、子どもが自分でやりたいと思って取り組む「あそび」にとことん夢中になることが何より大事であるということです。
がまんする力を育てる
とはいえ、自由にあそばせてばかりいるとわがままに育ってしまうのではないかと思われる方もおられると思います。
幼児のがまんについて、「マシュマロテスト」という有名な実験があります。4歳児に「今すぐ1個のマシュマロを食べるか、一定時間がまんすれば2個もらえるか」を選ばせる実験です。
この実験では、がまんできた子どもは将来的に学業成績が高く、社会的な成功を収める傾向があることがわかりました。
ただし、厳しいしつけだけでは「がまんする力」は育ちません。重要なのは、子どもが自分で気持ちをコントロールできる環境を作ることです。
しつけの効果と実践例については▶️「コスパがいい教育投資はいつ?今こそ考えるしつけの重要性」
非認知能力を育てる「あそび」の具体例
では、どんな遊びが非認知能力を育てるのでしょうか?ここでは、家庭でも簡単に取り入れられる遊びをご紹介します。
1. 外遊び
鬼ごっこやボール遊び、かけっこなど、体をたくさん動かす遊びは、協調性や忍耐力を育てるのに最適です。
2. ごっこあそび
おままごとやヒーローごっこなどの「ごっこあそび」は、想像力やコミュニケーション能力を育てるのに効果的です。
3. 自然とのふれあい
公園や森で木の実を拾ったり、虫を観察したりすることで、五感をフルに使い、探求心や好奇心が刺激されます。
4. 工作や創作活動
紙を切ったり、のりで貼ったりする工作遊びは、手先の発達や集中力の向上に役立ちます。
5. 絵本の読み聞かせ
絵本を読んであげることで、言語能力や想像力、文化への親しみを育てると同時に、親子のコミュニケーションの時間にもなります。
6. 大人と一緒に遊ぶ
子どもは大人と遊ぶことで、新しい考え方やルールを学びます。積極的に関わり、一緒に楽しみましょう。
まとめ
乳幼児期に五感をフルに使ってあそびに夢中になることで、就学後のあらゆる能力の土台が作られます。近年は、裸足で歩いたことがなかったり、視覚・聴覚に頼ったあそびしかしていなかったりする子どもが増えており、後々の成長に影響を及ぼすこともあります。
今、この瞬間にしか伸ばせない能力に目を向け、たくさんのあそびを通してのびのびと育ってほしいですね。
子どもの非認知能力を育てるために、ぜひ日々の遊びを工夫してみてください。