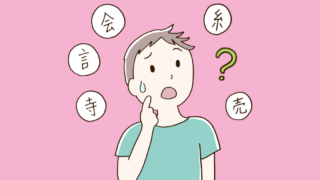食べ物を投げたり、ティッシュを全部出してしまったり、机によじ登ったり…。
「なんでこんなことするの?」と思うような行動も、実は能力が最も伸びる一生に一度の“敏感期”かもしれません。
とはいえ、毎食投げられたり、危ないところに登られたりすると、なかなか平穏には過ごせませんよね。
今回はそんな“敏感期”を見逃さず、日常生活を心穏やかに、そして子どもの成長を楽しくサポートするために、『5歳までの魔法の「おしごと」』という書籍を参考に、「モンテッソーリ流の育て方」をご紹介します。
モンテッソーリ教育とは?子どもが「自分で育つ」ための環境
最近よく耳にするモンテッソーリ教育は、子どもが自分自身の力で育っていくための「環境」と「機会」を与える教育法です。
この中で重要視されているのが「敏感期」という概念。運動・感覚・言語など、特定の能力がぐんと伸びる時期で、このタイミングに子どもはある特定の事柄に強い興味を持ち、繰り返し取り組むようになります。
子育てをしていると、「なぜこの行動を繰り返すの?」と思う場面がありますが、それこそが敏感期のサイン。見守ることで、大きな成長につながるのです。
「5歳までのしつけや環境が、人生を決める」
ノーベル経済学賞を受賞したヘックマン博士の研究では、「5歳までの育ちがその後の人生を左右する」という結果が出ています。
ドイツの教育学者フレーベルも「子どもは5歳までにその生涯に学ぶすべてを学び終える」と語っており、まさに幼児期は人間の土台づくりの時期だと言えるでしょう。
しつけの重要性とその効果については▶️「コスパがいい教育投資はいつ?今こそ考えるしつけの重要性」
五感と運動能力が一緒に育つことで、心も育つ
幼児期は、脳の発達が著しい時期です。特に五感を使って体をたくさん動かす経験は、脳のバランスのよい発達に欠かせません。
この時期に、見る・聞く・触れる・嗅ぐ・味わうといった感覚と、手を動かす・歩く・つかむ・運ぶといった運動が連動して育つことで、子どもはどんどん器用になっていきます。
そして、基本動作がしっかりと身につくと、「自分でやってみたい!」という意欲が育ち、それが成功体験につながることで、自己肯定感も自然と高まっていきます。
特別なおもちゃはいらない。日常が最高の教材
こういった力を育てるのに、高価な知育玩具や特別な教材は必要ありません。
子どもにとっては、日常生活のすべてが“はじめて”の体験であり、貴重な学びのチャンスです。
大人にとっては何気ない行動──例えば、コップに水を注ぐ、タオルを畳む、落ち葉を拾う、ボタンを留めるなども、子どもにとっては大切な「おしごと」です。
その「おしごと」を通して、体を使う力、集中力、達成感、感覚の統合といった、あらゆる基礎力が自然と育まれていくのです。
「おしごと」が育てる力とは?
自己効力感:「自分ならできる」の気持ち
日常生活の中で「おしごと」を通してトライアンドエラーを繰り返し、小さな成功体験を積むことで、「自分はできる」という自己効力感が育まれます。
感情のコントロール
子どもが遊びや作業に集中しているとき、それを止めるのは難しいですよね。そんなときに使えるのが「終わったら、終わりにしてね」という言葉。自分で終わりを決めていいよという意味です。
その言葉をかけたら、子どもが終わりにすると決めるまでぐっと我慢。この経験をさせてあげると、他のことでも自分で終わりにできるようになっていきます。
とは言っても癇癪を起こすこともあると思います。そんな時も「思いっきり泣いた後に、気持ちを切り替える」というプロセスを経ることで、徐々に感情のコントロールができるようになっていきます。
学びの意欲・自己決定力
親が「やらせたいこと」を与えるのではなく、子ども自身が「やりたいこと」に取り組むことで、思考力・継続力・自信につながっていきます。
子どもなら誰しもが学びへの意欲を持っていますが、やりたいことが制限されたりすることで、大きくなるにつれて学びへの楽しみが小さくなってしまうことがあります。いつまでも楽しく進んで学び続けてもらうためには、自己決定力を育て、集中し、自分の頭で考え、行動できる力を育てることが重要です。
「おしごと」を任せる前に知っておきたい、子どもの心のこと
「子どもがやりたいことを好きなだけやらせるなんて、わがままに育つんじゃないか」と思われる方もいるかもしれません。ですが、ここでぜひ理解しておいていただきたいのが、「甘え」と「甘やかし」はまったく違うということです。
「甘えさせる」とは?
甘えさせるというのは、子どもの気持ちやペースに寄り添い、安心できる環境を整えること。
たとえば…
- 難しいことを手伝ってあげる
- できるようになるまでそっと見守る
- 「抱っこしてほしい」「聞いてほしい」「見てほしい」という情緒的な欲求に応える
こうした心の土台を支える関わりこそが、子どもを自立へと導く第一歩になります。
「甘やかす」とは?
一方で甘やかすとは、大人の都合で先回りして子どもの成長の機会を奪ってしまうこと。
- 汚されるのが嫌だから子どもの代わりにやってしまう
- 我慢させるのが可哀想だからと、言われたままに買い与える
- 泣かれるのが嫌で、子どもに考える機会を与えずすぐに口出ししてしまう
これは「自分でやってみる」「失敗して学ぶ」という子どもの大切な力を摘んでしまう行為です。
甘えられた子は、自立できる
幼児期にしっかり甘えさせてもらえた子は、安心して自立していきます。
たとえば、すでにできる着替えや食事でも、「やってほしい」と言ってくることがありますよね。
これは、「できるけど、今は甘えたい」「まだちょっと不安」という、自立までのプロセスの一部なのです。
そのタイミングで受け止めてあげることで、子どもは「必要なときは助けてもらえる」という信頼感を持ち、やがて自分の力でやろうという気持ちが育ちます。
イヤイヤ期は「わがまま」ではなく「成長の証」
「全然言うことを聞かない」「癇癪を起こしてばかり」…そんな時期もあると思います。
でもそれは、我慢ができないからではなく、脳が未発達なだけ。
イヤイヤ期は最も意欲が高まり、自我が芽生えている“黄金期”と言われており、決して悪いことではありません。
毎回ではなくても大丈夫です。親に心の余裕があるときに、「やりたい気持ちはわかるよ」と言葉で受け止めてあげるだけでも、子どもにとっては安心できる大切な経験になります。
イヤイヤをぶつけられるのは、信頼している相手にだけです。信頼関係がしっかり築けている証でもあります。
今は大変でも、必ず終わりがやってきます。
その時期にたっぷりと「甘えられる環境」を整えてあげることが、将来の自立の土台になります。
「おしごと」を任せるときのポイント
- 子どもサイズの道具を用意する(小さな手に合ったサイズ)
- 注意が逸れるもの(音・テレビ・余計なおもちゃなど)は片付ける
- 失敗しても大丈夫なように、新聞紙やトレーを活用
- 口出しをせず、最後まで見守る
- 片付けまでが「おしごと」。親が先に片付けないよう注意
年齢別・シチュエーション別の「おしごと」も参考に
書籍『5歳までの魔法の「おしごと」』では、年齢や場面別におすすめの「おしごと」が紹介されています。
たとえば、ファスナーやボタン、靴ひも結びなどは、着ている状態でやるよりも、脱いでいるときに練習する「おしごと」として行うとスムーズです。
これは「困難の独立化」と呼ばれ、大人の学びにも応用できる考え方です。
遊びでも非認知能力が伸ばせます!▶️「子どもの非認知能力を育てる遊びとは?主体性を伸ばす方法」
まとめ:日常はすべて「おしごと」になる
子どもにとって、日常はすべてが“初めて”の連続。
投げたり、開けたり、登ったり…それらすべてが学びのチャンスです。
「これは“おしごと”なんだ」と思えば、イライラしてしまう日々も少し心に余裕が持てるかもしれません。
今しかない“敏感期”を、大切にしていきたいですね。