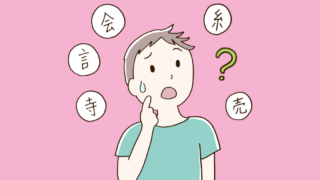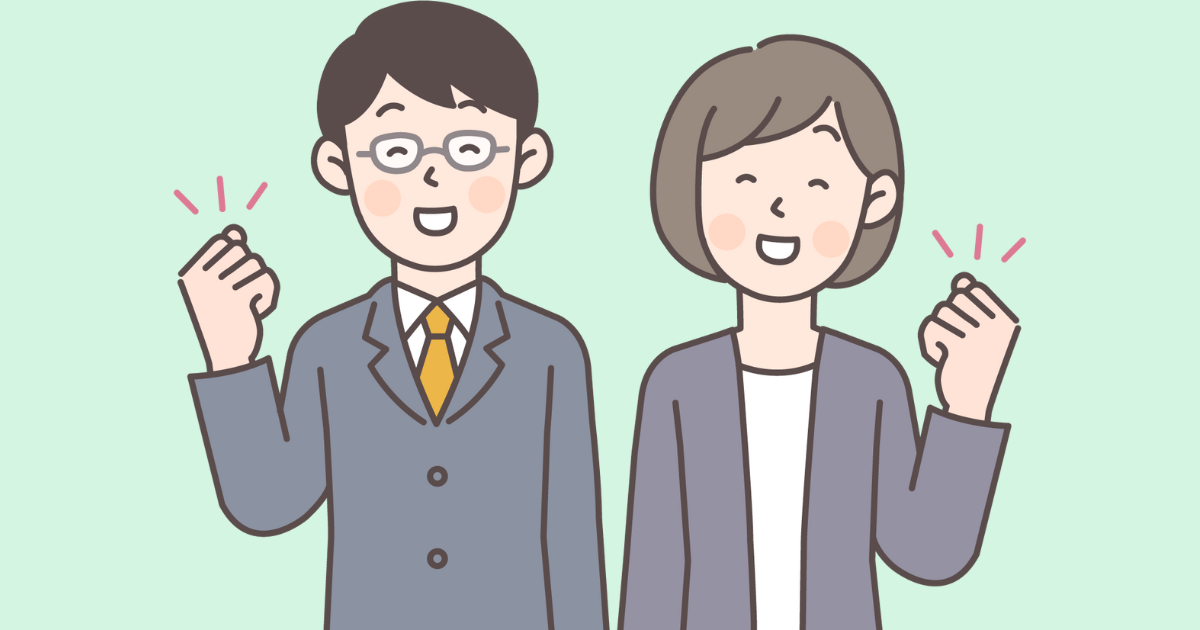令和の子育てトレンドとして注目されている「非認知能力」。
ペーパーテストでは測れない力と言われているものの、具体的に何をどうすればいいのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、科学的根拠に基づいて非認知能力をわかりやすく解説し、実践方法まで紹介してくれる良書、『子どもの才能を伸ばす 最高の子育て』をご紹介します。
子育てのゴールは「自立」——これからの時代に必要な力
本書では、子育ての最終目標を「子どもの自立」と定義しています。
つまり、自分の足で立ち、自分の意思で人生を歩んでいける力です。
そのために必要な力として紹介されているのが、今注目されている非認知能力。
自分の感情をコントロールする力、他者と協力できる力、粘り強く取り組む力など、学力では測れない「生きる力」がそこに含まれます。
なぜ今、非認知能力なのか?──背景にある研究とは
非認知能力が注目されたきっかけは、ノーベル賞経済学者ジェームズ・ヘックマンによる1962年からの調査研究です。
貧困家庭の就学前の子どもたちに質の高い教育を提供し、その後数十年にわたって追跡調査を行ったところ、幼児期に育まれた非認知能力が学歴や収入、社会的成功に大きな影響を与えることが明らかになりました。
実際、企業が求める新入社員のスキルでも、コミュニケーション力・主体性・チャレンジ精神など、非認知能力に支えられた社会的スキルが重視されています。
コスパで考える教育投資について▶️「コスパがいい教育投資はいつ?今こそ考えるしつけの重要性」
日本の子どもに足りないもの
OECDによる2012年の学習到達度調査(PISA)で日本は学力1位となりましたが、その後、学力の低下とともに、学習意欲の低さが大きな課題として浮き彫りになりました。
学びに楽しさを感じられず、自己肯定感が低いままでは、ウェルビーイング(より良く生きる)を感じられる人生を築くことは困難です。
自分への充足感が得られてこそ、他者への思いやりや、社会全体に目を向ける力が育ちます。
その基盤を作るのが、非認知能力なのです。
非認知能力を伸ばす遊びについて▶️「子どもの非認知能力を育てる遊びとは?主体性を伸ばす方法」
認知能力も、性格の良さも——どちらも育てる方法がある
本書では、「認知能力と非認知能力、どちらも高い子」を育てるための方法が紹介されています。
そのカギとなるのが、家庭での過ごし方です。
家庭は「習慣の学校」、親は「習慣の教師」
福沢諭吉が残した有名な言葉に「一家は習慣の学校なり、父母は習慣の教師なり」というものがあります。
つまり、家庭こそが最も影響力のある教育の場なのです。
アメリカのECLS-Bという調査では、家族と歌ったり遊んだり、夕食を一緒に取る家庭の子どもたちは、感情理解能力が高いことがわかりました。
非認知能力が伸びる肯定的養育とは
「肯定的養育」とは、以下のような関わり方を指します。
- 子どもとたくさん会話をする
- 一緒に遊ぶ・喜びを共有する
- 褒める・意見を尊重する
反対に、否定的養育は過干渉や一貫性のないしつけ、体罰などを含み、子どもの精神に悪影響を与えると言われています。
本書には、家庭環境チェックリストも掲載されており、今の自分たちの子育てを振り返るヒントにもなります。
将来を左右する3歳までの言語環境について▶️「3歳までに3000万語の格差を埋める「4つのT」:親子で言葉の豊かさを育む方法」
愛着(アタッチメント)がすべての土台になる
非認知能力を高める上で重要なのが、基本的信頼感です。
その基盤になるのが、親子の愛着(アタッチメント)。
愛着は、赤ちゃん期にだけ築かれるものではありません。
何歳からでも築き直すことができるということが、近年の脳科学で明らかになっています。
親以外にも、配偶者や職場の上司など、愛着は生涯にわたって変化しながら育まれるもの。
だからこそ、今からでも遅くないのです。
愛着形成に効果的な記事はこちら
絵本と童謡▶️「「三つ子の魂百まで」実践!歌200曲と読み聞かせ1万回のすすめ」
ベビーマッサージ▶️「ベビーマッサージで楽しいひとときを!赤ちゃんとの触れ合いで心も体も健康に!」
これからの時代に求められる「共有型の子育て」
これまでのような親が子どもを支配する子育てではなく、「共有型の子育て」へとシフトしていく必要があります。
子どもと向き合い、会話し、触れ合い、共に過ごす時間が、家庭を「安全基地」に変えていきます。
そして何より大切なのは、親自身が前向きに、人生を楽しんでいること。
子どもは親の背中を見ています。
毎日が完璧でなくても大丈夫。
まずは「自分が笑顔でいられること」から始めてみましょう。
まとめ|非認知能力は、子どもと親の毎日の関わりから育つ
非認知能力とは、生きる力そのもの。
学力だけでは補えない、人としての土台です。
本書『子どもの才能を伸ばす 最高の子育て』には、科学的根拠に基づいた実践的なヒントが詰まっています。
ふわっとして捉えづらい「非認知能力」というテーマを、今日からの子育てに活かしたい方におすすめの1冊です。