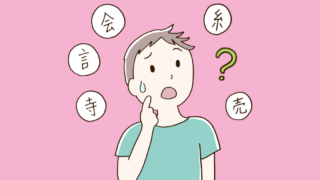日本の子育てにおいては、しばしば「一億総評論家」と言われる状況にあります。誰もが教育を受けてきたからこそ、それぞれの経験を基にした意見が飛び交い、子育てや教育に関する情報が溢れています。しかし、そうした情報の多くは文化や慣習に基づいており、具体的な科学的根拠に欠けることが多いように感じます。私が目指すのは、主観的な成功体験ではなく、科学的根拠に基づいた子育てです。
幼児教室で様々なお子さんを見てきましたが、伸びやすいお子さんの共通点は、親御さんが明確に子育ての見通しを立てていて、ご夫婦でしっかりと共有できているということでした。そこで今回紹介するのが、教育に関する様々な疑問にエビデンスをもとに答えてくれる「『学力』の経済学」という一冊です。この本は、教育の重要なポイントを経済学の視点から紐解き、親が子育て方針を立てるための貴重なガイドを提供してくれます。
巷に溢れる子育て情報の「根拠の欠如」
インターネットや雑誌でよく見かける「子どもをご褒美で釣ってはいけない」というアドバイス。本当にそうなのでしょうか?「ご褒美が良くない」というのは、内発的動機付けを重視する考え方に基づいていますが、必ずしもその見解が正しいとは限りません。
「『学力』の経済学」では、このような教育に関する通説に対して、経済学的なエビデンスに基づいた分析を行い、正しい判断基準を提供してくれます。例えば、場合によっては適切なご褒美が子どもの学習や行動にプラスの影響を与えることが示されています。こうした事実を知ることで、表面的なアドバイスに振り回されず、本質を見極める力を身につけることができます。
教育にはいつ投資すべきか?「適時教育」の重要性
「『学力』の経済学」で特に興味深かったのは、教育にはいつ投資すべきかという問いに対する答えです。この本では、幼児教育に投資を行うことが最も効果的であると明確に示されています。私自身、講師の経験から、幼児期の教育が子どもの成長に与える影響が大きいことを実感していましたが、それが経済学的なデータで裏付けられているという点に大きな納得感を得ました。
ただし、幼児教育とは単に「早期に教育を始めること」を意味するのではありません。むしろ、重要なのは「適時教育」です。つまり、子どもの成長段階に応じて、その時々に適した内容を教えることが大切です。単に早く教育を始めれば良いというものではなく、その子の発達段階に合わせた適切な教育を行うことが、長期的な成長にとって最も効果的なのです。
この考え方は、私が働いていた幼児教室でも実感していたことです。幼児期の子どもには、その時々に応じた教育が必要であり、ただ早期に教育を詰め込むだけでは十分な成果は得られません。「適時教育」という視点を持つことが、子どもの成長を支えるための最良のアプローチです。
子どものペースに合わせた適時教育の関連記事
就学前にしか育てられないスキル▶️「子どもの非認知能力を育てる遊びとは?主体性を伸ばす方法」
日常生活の中で伸ばす▶️「5歳までの敏感期を逃さない!モンテッソーリ流“おしごと”で育つ力」
シュタイナー教育▶️「シュタイナー教育ってどんな考え方?日常に取り入れられるエッセンス」
パートナーと子育ての方針を話し合う重要性
「『学力』の経済学」は、妊娠中の比較的時間のある時期にじっくりと読み、子育ての方針を立てるためのガイドとして非常に役立つ一冊です。この時期にこそ、親としてどのような教育方針を持つべきかをパートナーと話し合うことが重要です。
特に、子どもの誕生から大学までの大まかな目安を、二人で一緒に考え、話し合いを通じて共有することが大切です。ただし、最初に立てた目安に固執する必要はありません。子どもの成長や状況に応じて、教育方針を柔軟に変更・軌道修正していくことは自然なことであり、むしろそれが正しい姿勢です。変化を前提にしつつ、最初の段階では「ざっくりとした方針」を立てることが肝要です。
こうした話し合いを通じて、親同士の理解と協力が深まり、子どもにとっても一貫性のある環境を提供できるようになります。
しつけの重要性とその効果
もう一つ注目したのは、「しつけ」の重要性についてです。多くの親がしつけを重要視しているものの、その具体的な効果についてはあまり語られていないように感じます。
中には、しつけなんて、挨拶なんて、意味がないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが(私のパートナーはそうでした)、しつけを通じて培われる自律心や責任感が、仕事や社会での成功に繋がるというのです。
がまんについての実験「マシュマロテスト」
幼児のがまんについて、「マシュマロテスト」という有名な実験があります。4歳児に「今すぐ1個のマシュマロを食べるか、一定時間がまんすれば2個もらえるか」を選ばせる実験です。
この実験で、がまんできた子どもは将来的に学業成績が高く、社会的な成功を収める傾向があることがわかりました。
「がまんする力」というと、「ルールを守る」「親の言うことを聞く」「静かに待てる」といった行動を思い浮かべがちですが、実はもっと本質的なものです。
「がまんする力」とは、自分の気持ちをコントロールし、状況に応じて行動を調整する力のことです。
厳しいしつけは逆効果?
「しつけ」と聞くと、厳しく叱ったり、ルールを徹底させたりすることを思い浮かべるかもしれません。しかし、厳しく叱るだけでは、本当の意味での「がまんする力」は育ちません。
例えば、ある子どもが「おもちゃを買ってほしい!」と泣きわめいたとします。親が厳しく「泣いちゃダメ!がまんしなさい!」と叱った場合、子どもは「叱られるのが怖いから泣かないでおこう」と学びます。
しかし、これは本当の「がまん」ではありません。ただ単に、恐怖や外的な圧力で抑え込まれているだけです。このような状態では、自分の気持ちを理解して調整する力が育たず、将来的にストレスをうまく処理できない可能性があります。
自分の感情をコントロールする力を育てる
では、どうすれば子どもが本当の意味で「がまんする力」を身につけられるのでしょうか?
ポイントは、気分のオン・オフの切り替えをサポートすることです。
例えば、子どもが「おもちゃを買って!」と訴えたときに、ただ叱るのではなく、次のように接してみてください。
- 「本当にこのおもちゃが欲しいんだね。どんなところが気に入ったの?」(気持ちを言葉にするサポート)
- 「今日は買えないけど、お誕生日のときに考えようか?」(代替案を提案)
- 「このおもちゃ、あとで一緒にお店で見るだけでも楽しいかもね」(気持ちの切り替えを促す)
このように、子どもが自分の気持ちを認識し、それを自分で整理できるようにサポートしてあげることが大切です。
育児書の活用法:エビデンスを元に柔軟に取り入れる
育児書を読む際、私はその内容をそのまま鵜呑みにするのではなく、考え方のエッセンスを理解し、自分の家庭にどう活かすかを考えています。この本でも、全てをそのまま実行するというより、科学的根拠に基づいたアプローチを自分なりにアレンジすることが大事だと感じました。
例えば、「ご褒美を使う教育法」に対するエビデンスを知ったうえで、それを子どもの性格や家庭環境に合わせて応用するのが理想的な取り入れ方です。エビデンスを基にした柔軟な対応こそが、賢い子育てに必要な視点だと思います。
まとめ
「『学力』の経済学」は、妊娠中や育児中に子育ての方針を立てたいと考えているご夫婦にとって、非常に有益な情報を提供してくれる一冊です。特に、パートナーと一緒に子どもの将来について話し合い、柔軟な方針を共有するための良い機会を提供してくれるでしょう。
この本を読んで、あなたも賢い子育てのための見通しを立ててみませんか?